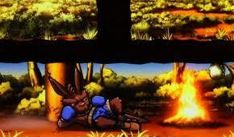では、演出面はどうであろう。
これが、ほぼ動かない。
基本的には、
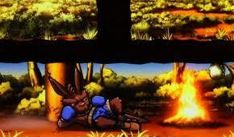
こうしているだけである。
ボーナス終了後にちょっとアクティブになるくらいだ。
ただし、まったく演出がないわけでもない。
ふっと気が向いたら、木をサンドバッグ代わりに叩き、時には大きなカットインから派手目な演出が起きる。
昨今のAT機のゲーム性を鑑みれば、アテにならないとお思いになる読者も多いことだろう。
どうせ、派手な演出でスイカだとかチェリーが落ちるだけなのだろうと。
否、バガナックルーに関していえば、そうではない。
大きな演出が起きた時は、実際なにかコトが起きている・・・ことが多い。
体感だが。
リールの項でも書かせていただいたが、基本的には「3つ」リールをとめた時の違和感。
ここに集約されているのが、バガナックルーである。
なので、液晶演出に依存しない。
いや、依存しないわけではない。
演出と出目のバランスがいいのだ。
後のゲーム性の項でまた紹介させていただくが、
とかく演出と出目が良い形で相互に依存しあっている。
さしずめ落語の演目「芝浜」に出てくる夫婦くらいに、お互いがお互いを必要としているようにできているのだ。
この演出バランスが個人的にはツボだ。
何も起きないわけではないが、何かが起きた時はなにかきちんと意味がある。
なにも起きない時にも、それなりに意味があるあたりがもうたまらんのだ。
打ち手のこちらとしては、「ワクワク」と「モヤモヤ」の繰り返しなのだ。
この辺はゲーム性を理解していただかないとわからない。
というわけで、ゲーム性の紹介に移ろう。
次のページへ
回胴小噺_楽屋裏 メニューへ戻る