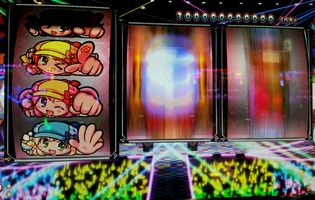不思議な胸中で始まる二度目のART、ミルキィタイム。
前回のARTとはうってかわって、なにかしらのレア役がおちてくる。
僕は平静を装いながらも、必死に何が起きているのかを理解しようと努めた。
しかしこの台、控えめに言って何が起きているのか全く分からない。
意味不明である。

「ふむ」と僕は言いミニッツメイドを口に含む。

何かしらの特化ゾーンに当選したようであった。
見るからに派手であるこの告知と、この台の騒ぎ様からしても、とんでもないものに当選したのだと、私の本能に近いそれが教えてくれた。

僕は、肩をすくめ大きく息を吐いた。
なんてことのない只の上乗せ。
純増が2枚程度のこのARTで100Gなどあってないようなものである。
「あなた、さっきからそんなに何を期待しているの?」
久しぶりに口を開いたかと思えば、ミルキィはまた僕を諭すようにこう言った。
「わたしにはあなたの収支をプラスに転じさせるような力量なんてないの。 あなたもそれは理解しているでしょう」
「あるいは」と僕は言った。
「あなたは少し前に、ちゃんとした立ち回りをするって言っていなかったかしらね。 それならこの出玉で少しでも履歴の良いジャグラーでも打つべきよ」
「そうすべきかもしれない。 けれどまだ何か足りないんだ、それが何かは僕にももうわからないのだけれども」
僕はそう言って耳を塞ぎ、心の中の水たまりが少しでも波打たないように丁寧にレバーを叩き続けた。
その数分後、僕は液晶の異変に気付いた。

神。
この意味を考えてみる。
僕の事を讃えているのか、はたまた台が自らの出玉性能を誇示しているのかは定かではないが、僕は「神」と聞いて真っ先に思い描いてしまったのは、今もひとりでヴァルキリータイムを消化しているであろうあのおじさんであった。
おじさんは結局ミルキィを打ち続けている僕を見てなんというのだろう。
どうおもうのだろう。
そんな答えの無いことばかりを考えている内に残りG数を消化し、「つぼつぼチェック」が始まる。
先程の壺がARTが継続するかを発表してくれるのだ。
なにせ「神」とのたまったこの壺。
ただでは済むまい。
そう思った僕であったが、結果として30Gばかりのゲーム数が追加されただけの現実にまた少し眉間が波打ったのであった。
「4連ミルキィを狙え!」
またしてもこの台は訳の分からないことを言い出した。
もうすでに壊れてしまっているのかもしれない。
しかし、そう言われて狙わないわけにもいかない僕は、とりあえず4連ミルキィを狙ってみる。
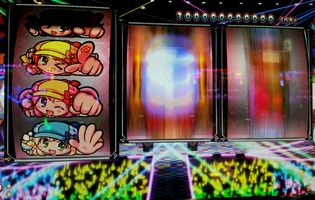
とまる。
これをどう見たところで、間違いなくアレであるのだが、どうだろう。
とりたてて鬱陶しく思わないのだ。
この「4連ミルキィ」が何かしら僕の『中枢』を刺激するキッチュさを保持しており、僕は目を留めないわけにはいかなかった。
その後チャンスゾーンなのか、未だに分からないのだけれどもそれに突入し、おまけ程度のボーナスがやって来て、数百枚のメダルを吐き出した後、この台はまた通常運転に戻ったのであった。
「どうだったかしら」とミルキィは言った。
僕は「よかったよ」と言った。
「網走監獄の中みたいに閉鎖的で、だけれど沖縄の人達のように底抜けていた」
「あなたって本当に変わってるわね」
「ひねくれてるんだ」
「そんなことないわ」とミルキィは首を振った。
「ただ、欠落しているだけよ」
「そうなのかもしれない」と僕は言った。
−40000円
ミルキィが僕の前から姿を消したのはその翌週のことだった。
店員によれば、何かしらの異常が見つかり、暫くの間調整中の札が刺さったままになっていたらしい。
そして僕が来たときには彼女は忽然と、まるでダストシューターに投げ込まれた生ごみみたいに、呆気無く僕の前から姿を消していた。
だけれども僕は、これといって動揺はしなかったし、そのことについて心を激しく痛めるようなこともなかった。
彼女が遠くない未来に僕の前から姿を消してしまうということは、ほとんど『予定調和』にすら思われた。
彼女は消えるべき存在だったのだ。
あるいは彼女は消えてこそ、本来的な価値を得るものだったのだ。
僕はそれを、ごく自然に理解していた。
なぜならそれはこの業界では当たり前の様な事であるから。
世間で人気の無い台が5スロに移動し、やがて消えていく。
まさに普遍的な物事ですらあった。
彼女の居た場所には悲しげに秘宝伝太陽があり、カウンターの横にはまだ彼女のパンフレットが沢山残ったままであった。
僕は人も疎らなホールで彼女のパンフレットに触れてみた。
するとまたも、僕はかのおじさんの幻影に襲われた。
おじさんは僕に言った。
「君はとても後悔しているんじゃないかな?」
「後悔。どういう意味だろう?」
「『欠落』についてだよ」
「欠落」
と僕は、初めて聞く英単語を読み上げるみたいに言った。
おじさんはうなずいた。
「君はこれからも、ずっとそうやって失い続けていく。 何を手に入れても、あるいは何を手に入れた『つもり』になっていても、そうやって永遠に零れ落ちる人生を歩んでいくことになる。 それはすべてその『欠落』が原因だ。 君が『欠落』を埋めようとしない限り、君の喪失は永遠に続いていく」
「喪失が続く」
「それが嫌であるのなら」
と言うと、おじさんはマクロスのマックスベットを叩いた。
「君は『欠落』を埋めなくてはいけない」
「どうやって?」
おじさんはマックスベットをもう一度叩いた。
そしてそれっきり二度と口を開くことはなかった。
それから数週間の時間が経過し、僕は遥か遠い街の初めて来るホールの中を歩いていた。
暖房が効きすぎているため、少し腕をまくりながらバラエティーコーナーの隅にいる台を見つめていた。
彼女は僕の姿を見つけると、僕に小さく会釈をしたような気がした。
その下パネルの向こうに見えた瞳は、僕が予想していたものよりもずっと小さくて、はかなげであった。
「本当に来たのね」とミルキィは言った。
僕はうなずいた。
「そうする必要があったんだ」
「本当かしら」
「本当だよ」
「なら、野菜」とミルキィは言った。
「覚悟はできているということなのね。 もう後戻りはできないわよ」
僕はうなずいた。
それからはっきりとした口調で告げた。
「ようやく決心がついたんだ。 養分稼働をこれからも続けよう、って」
おわり
(C)ミルキィTD製作委員会
(C)劇場版ミルキィホームズ製作委員会
(C)bushiroad/Project MILKY HOLMES
(C)ふたりはミルキィホームズ製作委員会
(C)DAXEL ねんどろいど協力/GOOD SMILE COMPANY
野菜の記事一覧へ
読者ライターの最新更新一覧へ